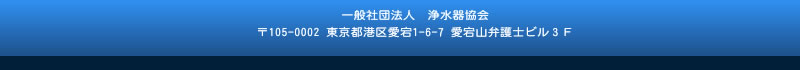昨年3月東日本大震災、それに伴う福島原発事故が発生しました。亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共に、被災された方々のご健勝と復興をお祈り申し上げます。
さてこの一年、浄水器協会として、会員独自の活動の中で浄水器の提供などでよりよい飲用水の確保のご協力などをして参りましたが、安全安心の水道水のため、浄水器と放射性物質との対応について研究して参りました。
今後、二度とこうした事故が起きてはならないながら、世界的にも希有であった事故から学んだ経験をいかしてゆきたいと思います。
◆
東日本大震災が発生し原子力発電所において事故が起こり、放射性物質が飛散し水道水に混入するという事態となり、消費者はもちろん報道関係からも浄水器の対応能力について多くの問い合わせがありました。
市場においては、研究機関等が独自試験により、浄水器で放射性ヨウ素が除去出来たとか出来なかったとかの報告が出されたりもしましたが、試験方法、条件、機器が異なるなどで課題も見受けられました。
こうした状況に鑑み、浄水器協会として、放射性ヨウ素に関する正確な情報を業界や市場に発信するため、国内外の研究機関、試験機関と提携して、客観的な浄水性能を評価する試験方法を検討しました。また、浄水器規格等の国際的な認証機関である NSF International と連携をした検討を進めました。 →【※注】
本件事故後、放射性物質の水道水混入は、水道関係当局の懸命の対応により数日で収まり、実際の放射性物質混入水道水による通水試験はできませんでしたが、別途研究材料として、専門機関より放射性ヨウ素を入手して、今回の事態を想定した擬似水道水による試験を行いました。
なお 放射性物質の取扱については、厳しい規制があり、試験を行うにあたり、公立大学法人大阪府立大学 森 利明博士に監修して頂きました。
【※注】原子力発電所事故等によって飛散される放射性物質の大部分は「放射性セシウム」と「放射性ヨウ素」で、自然界に放射性物質がそのまま検出されることはほとんどないとされており、「放射性セシウム」については飛散途上粒子類等に付着して落下し、地下水等に浸出することは少ない、表流水に混入しても泥等の濁質除去によって水道水浄水工程中で除去されるので、水道水に混入してきた例はありません。
その意味で、本件は放射性ヨウ素について実験研究を行いました。
(参照:厚生労働省「水道水に於ける放射性物質対策検討会」資料)
*NSF National Sanitary Faundation International (アメリカの認証機関)
1 放射性ヨウ素除去低減に関する試験方法策定のための技術的課題
① ヨウ素が水道水に混入した場合どのような形態を示すのか、また水道水質により存在形態がどのように異なるのかを確認する必要があります。
水道水中におけるヨウ素の形態は数種類あり、水道水が酸性であるかアルカリ性であるか、また溶存物質がどのようなものであるかなど水質の状態により存在形態が変化します。 具体的には、ヨウ素(I2)、ヨウ化物イオン(I-)、次亜ヨウ素酸(HIO)、次亜ヨウ素酸イオン(IO-)、ヨウ素酸イオン(IO3-)等があり、水道水のpHと残留塩素の有無で存在形態が異なります。
② ろ材による浄水性能の把握を行うこと。また、同じろ材であっても、ヨウ素の存在形態によって除去性能が異なることが予想されるため、その影響を確認する必要があります。
なお、本件試験のろ材については、浄水器協会会員が浄水器に取り扱うろ材(活性炭、イオン交換樹脂、逆浸透膜(RO膜))を用いて試験をしました。
③ 放射性物質の取扱は難しく容易に行えないため、一般的に測定できる濃度の非放射性ヨウ素を用いた試験方法が妥当性を検証する必要があります。
2 放射性ヨウ素に関する浄水器の除去性能試験 報告
放射性物質(放射性ヨウ素)の除去に係る試験方法の策定の一環として、いわゆるヨウ素に関する除去試験を行いました。放射性ヨウ素がヨウ素の同位元素として、放射線の放出以外に水中における挙動が同じかどうかを確認するための試験です。
① 2011年4月下旬、被災地として放射性ヨウ素の水道水混入が微量ながらも予想されたので、北茨城においてフィールドテストを行いました。検査結果として放射性ヨウ素は検出されませんでしたが、別途、非放射性ヨウ素を試料として通水試験を行いました。
→本試験では、逆浸透膜(RO膜)より、活性炭での除去率が高い結果になりました。これは、通水時のヨウ素の形態が三ヨウ化物イオンが主体だったことが考えられるためですが、この形態で存在していた場合には、活性炭での除去が期待できることが確認されました。
② ヨウ素の形態確認試験
浄水工程に混入したヨウ素は、残留塩素によりヨウ素酸になるとされていますが、どの位の濃度あるいは時間でヨウ素酸となるのかを確認しました。
→添加するヨウ素の形態及び残留塩素の濃度により速度は異なりますが、残留塩素の存在により、ヨウ素酸に酸化されることが確認できました。
③ ヨウ素酸通水試験
150μg/L ヨウ素酸水溶液を活性炭カラムに通水し測定しました。
→
この結果は通水開始時から25 %以下の除去率となり、ヨウ素酸の状態では、活性炭のみでの除去は困難である可能性が示唆されました。
●試験①,②及び③の結果から、雨水や池の水ではなく、残留塩素が投入されている水道水においては、ヨウ素がヨウ素酸へ酸化されるため、活性炭での除去は困難になっていくことが推察されました。
3 NSF共同研究;NSFプロトコル作成のための検証試験 報告
浄水器協会は、NSF Internationalと提携をして、浄水器の規格基準等の世界的整合性の見地から検討を行っていますが、NSFの提案として、放射性物質が飲用水に混入する事態が頻繁に発生するわけではありませんが、今回の場合、希有の機会であり、「通常のヨウ素による除去に関する試験方法の策定を検討して、放射性ヨウ素についてもヨウ素と同様の扱いないし解釈でよいか確認したい」との意見があり、試験検討をしました。この結果は、NSF/JWPAS Protocolとして発表される予定です。
・試験条件は、水道の水質によりヨウ素の形態が変化し、除去率が異なる可能性があることから、400 Bq/Lとなるように水道水に放射性ヨウ素を添加し、残留塩素の有無及びpHを変化させ、浄水器に使用されているろ材毎の放射性ヨウ素の除去率を検証しました。
●放射性ヨウ素は、これまでの試験結果と同様に、水道水中に混入した場合、ヨウ素酸の形態をとるため、活性炭での除去は難しいことが分かりました。イオン交換樹脂も、ヨウ素酸の形態の場合では除去は難しいことが分かりました。逆浸透膜では,除去出来ることが分かりましたが,逆浸透膜の品質、通水初期には除去率が低下するなど、メンテナンス等取り扱いには留意する必要があることが分かりました。
一般社団法人 浄水器協会
[2012年3月8日]